生成AI技術は日々発展を遂げ,プログラムコードの自動生成への応用の期待がある.高性能計算(HPC)においては高性能を達成するため,アーキテクチャ・システムごとに性能最適化されたコードの開発が重要である.本プロジェクトではアーキテクチャごとに最適化された高性能コードの生成AIによる自動生成技術を開発し,科学技術計算の持続的な性能向上の達成を実現するため,名古屋大学情報基盤センターを中心とした日本国内の大学・研究所による共同研究を実施する.
スーパーコンピュータ「富岳」に代表されるスーパーコンピュータ技術の進展により,ソフトウェアの高性能化が進んでいる.現状は,Fortranによる信頼性の高いコードと,MPI (Message Passing Interface) による分散並列化の技術によって支えられている。一方,近年のAIブームでGPU (Graphics Processing Unit) の普及が進み,電力効率に優れたGPUの数値計算への活用が期待されている.しかしHPCを支える人材は減少しており,GPU実装やHPCプログラミングができる研究者は少ない.この現状打破のため,本プロジェクトではLLMやRAG (Retrieval Augmented Generation) を活用したコード生成AI技術により高性能HPCソフトウェアの開発効率を高める革新的AI基盤の開発を目指す。さらに当研究室で研究されている,混合精度演算,自動性能チューニング (Auto-tuning, AT),および説明可能AI(XAI)の技術を統合することで,持続可能なHPCソフトウェア基盤の構築を目指す.
また,セキュリティや研究上の制約でローカルLLMしか使えない局面は多い.HPC-GENIEプロジェクトでは,ローカルLLMの活用方法も研究対象とする.また,我が国で開発されている和製LLMの適用も考慮し研究を進める.特に,国産Swallow LLMのローカルLLMへの適用を強力に推進し,国産AIエージェント基盤の開発を目指す.
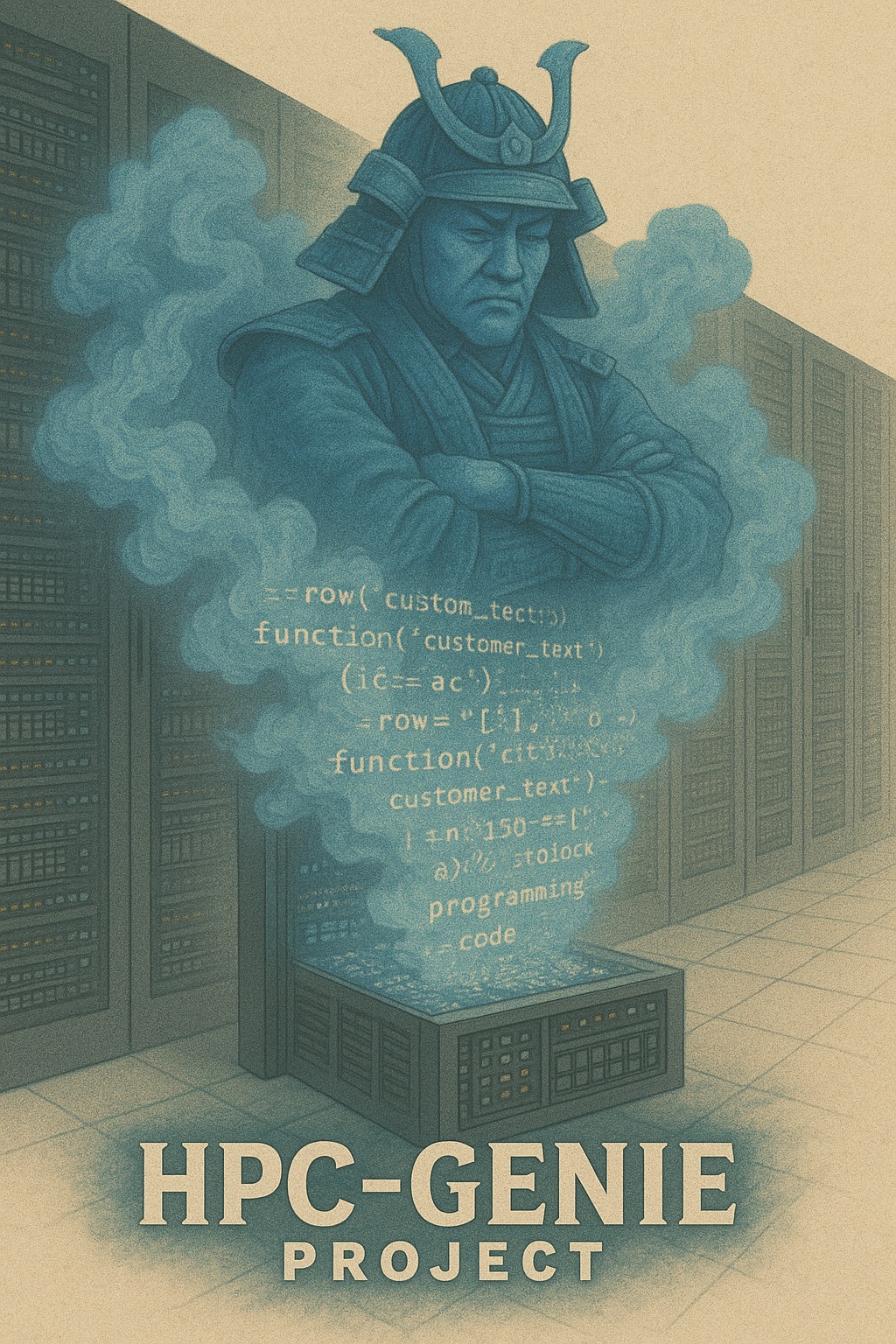 Generated by ChatGPT-4o
Generated by ChatGPT-4o開発対象
- HPCコード生成を実現するためのプロンプトエンジニアリング方式
- 複数のLLMが利用できるCLI (Command Line Interface)の開発、及び、ソフトウェア自動チューニング(Auto-tuning, AT)機能との連携
- HPCコード生成を実現するためのRAG (Retrieval Augmented Generation) 、およびファインチューニング機能の開発
- HPCコード生成を実現するためのローカルLLMの活用方式
- コード生成AIによる、精度保証、混合精度演算、説明可能AI(XAI)およびATコードの自動生成
- 開発するコード生成AI基盤/ツール群はオープンソース化を行い、ソフトウェアの持続可能性(Sustainability)を高める
研究発表(予定を含む)
- Tetsuya Hoshino, Shun-Ichiro Hayashi, Daichi Mukunoki, Takahiro Katagiri, Toshihiro Hanawa, Evaluating Claude Code's Coding and Test Automation for GPU Acceleration of a Legacy Fortran Application: A GeoFEM Case Study, The 1st International Workshop on Foundational Large Language Models Advances for HPC in Asia (LLM4HPCAsia 2026), Jan. 29, 2026 (accepted).
- Koki Morita, Daichi Mukunoki, Tetsuya Hoshino, Takahiro Katagiri, Evaluation of the Capability of Coding AI in Generating SYCL-Based Numerical Computation Codes for Intel GPUs, SCA/HPCAsia2026, poster session, Jan. 2026 (accepted).
- Ryo Mikasa, A Multi Agent System for Local LLM-Based HPC Code Generation, SCA/HPCAsia2026, poster session, Jan. 2026 (accepted).
- 片桐孝洋,「ソフトウェア自動チューニング研究の最前線 ~量子アニーラからコード生成AIエージェントまで~」,Quloudセミナー - HPC・AI応用編 -,2025年12月24日.
- 片桐孝洋、林俊一郎、森田光貴、椋木大地、星野哲也,HPC-GENIE:コード生成AI活用によるHPCコード自動生成プロジェクト,第17回自動チューニング技術の現状と応用に関するシンポジウム(ATTA2025),2025年12月23日.
- 椋木大地,森田光貴,林俊一郎,三笠諒,星野哲也,片桐孝洋,gpt-oss-120bを用いたコード自動最適化マルチエージェントシステムの試作,第255回システム・アーキテクチャ・第202回ハイパフォーマンスコンピューティング合同研究発表会,2025年12月15日.
- 林俊一郎,森田光貴,椋木大地,星野哲也,片桐孝洋.VibeCodeHPC:自動コード最適化CLI型マルチエージェント,第255回システム・アーキテクチャ・第202回ハイパフォーマンスコンピューティング合同研究発表会,2025年12月15日.
- Takahiro Katagiri, HPC-GENIE: A Multi-Agent Code Generation Platform Project Based on Context Engineering, JHPCN Field Workshop: State-of-the-Art in Code Generative AI for High-Performance Computing, Dec. 5, 2025.
- Tetsuya Hoshino, Evaluating Claude Code’s Coding and Test Automation for GPU Acceleration of a Legacy Fortran Application: A GeoFEM Case Study, JHPCN Field Workshop: State-of-the-Art in Code Generative AI for High-Performance Computing, Dec. 5, 2025.
- Shun-ichiro Hayashi, VibeCodeHPC: CLI-based multi-agents system for auto-tuning, JHPCN Field Workshop: State-of-the-Art in Code Generative AI for High-Performance Computing, Dec. 5, 2025.
- Daichi Mukunoki, Automatic Generation of Numerical Codes for GPUs Using LLMs, JHPCN Field Workshop: State-of-the-Art in Code Generative AI for High-Performance Computing, Dec. 5, 2025.
- Daichi Mukunoki, Automatic Generation and GPU Porting of Numerical Computation Codes Using Generative AI, 58th ASE Seminar, Dec. 1, 2025.
- Shun-ichiro Hayashi, Daichi Mukunoki, Tetsuya Hoshino, Satoshi Ohshima, Takahiro Katagiri, 3Dify: a Framework for Procedural 3D-CG Generation Assisted by LLMs Using MCP and RAG, arXiv preprint arXiv:2510.04536, October 2025.
- Shun-ichiro Hayashi, Koki Morita, Daichi Mukunoki, Tetsuya Hoshino, Takahiro Katagiri, VibeCodeHPC: An Agent-Based Iterative Prompting Auto-Tuner for HPC Code Generation Using LLMs, arXiv preprint arXiv:2510.00031, September 2025.
- 林俊一郎,森田光貴, 椋木大地,星野哲也,片桐孝洋,LLMによるコード自動最適化「VibeCodeHPC」の開発状況と実験が示したマルチエージェントの優位性,物性研究所ソフトウェア開発・高度化プロジェクト研究会 〜計算物質科学の発展を支えるオープンソースソフトウェアの開発と普及,ポスター発表,2025年10月20日.
- 椋木大地,林俊一郎,星野哲也 ,片桐孝洋,LLMを用いた数値計算コードの自動生成・自動性能最適化への挑戦と展望,物性研究所ソフトウェア開発・高度化プロジェクト研究会 〜計算物質科学の発展を支えるオープンソースソフトウェアの開発と普及,ポスター発表,2025年10月20日.
- Daichi Mukunoki, Challenges and Prospects in Automatic Generation of HPC Codes Using Generative AI, The 6th "FugakuNEXT" Application Seminar, Sep. 25, 2025.
- 林俊一郎,椋木大地,生成AIを活用した数値計算・HPCコード自動生成への挑戦と展望,2025年度第2回物性アプリオープンフォーラム,2025年9月29日.
- 星野哲也,林俊一郎,椋木大地,片桐孝洋,塙敏博,GeoFEMを対象としたClaudeCodeによるGPUコード開発の評価,第201回ハイパフォーマンスコンピューティング研究発表会,2025年9月29日.
- 片桐孝洋,林俊一郎,椋木大地,星野哲也,大島聡史,HPC-GENIE: コード生成AIを活用するHPCコードの自動生成と「富岳NEXT」への展開,日本物理学会第80回年次大会,2025年9月17日.
- 椋木大地,汎用LLMによるBLASコード自動生成能力の考察,第6回スーパーコンピュータ「不老」ユーザ会,2025年9月11日.
- 片桐孝洋,HPC-GENIE: LLMを利用したHPCコード自動生成プロジェクト ー概要とケーススタディー,日本応用数理学会 2025年度年会,2025年9月2日〜4日.
- 林俊一郎,椋木大地,星野哲也,片桐孝洋,HPC-GENIE: High-Performance Computing with Generative Neural Intelligence for Execution,xSIG 2025,ポスター発表,2025年8月(Poster Award).
- 椋木大地,林俊一郎,星野哲也,片桐孝洋,BLASコードを題材としたGPTモデルによる数値計算コード実装支援に関する考察,第200回ハイパフォーマンスコンピューティング研究発表会(SWoPP2025),2025年8月.
- 林俊一郎,椋木大地,大島聡史,片桐孝洋,星野哲也,MCP・RAGを用いたプロシージャル3D生成LLMエージェント3Difyの提案とスパコンの利用,第200回ハイパフォーマンスコンピューティング研究発表会(SWoPP2025),2025年8月.
- 椋木大地,LLMによるBLASコード生成に関する考察,第33回AT研究会オープンアカデミックセッション(ATOS33),2025年7月28日.
- 林俊一郎,DifyのLLMエージェントとRAGを用いたHPCコード生成の展望,第33回AT研究会オープンアカデミックセッション(ATOS33),2025年7月28日.
- 片桐孝洋,HPC-GENIE:コード生成AIを活用したHPCプログラム自動生成プロジェクト ーFortranからGPUコードの自動生成は可能か?ー,第33回AT研究会オープンアカデミックセッション(ATOS33),2025年7月28日.
- Daichi Mukunoki, Shun-ichiro Hayashi, Tetsuya Hoshino, Takahiro Katagiri, "Performance Evaluation of General Purpose Large Language Models for Basic Linear Algebra Subprograms Code Generation", arXiv preprint arXiv:2507.04697, July 2025.
- 林俊一郎,3Dify: 対話型分散フレームワーク ーRAGを用いたマルチDCC対応プロシージャル3D生成LLMエージェントー (3Dify: Distributed interactive framework - your LLM Agents for Multi-DCC Compatible Procedural 3D Generation with RAG -), 名古屋大学情報学部コンピュータ科学科情報システム系 卒業論文,2025年2月.
- 林俊一郎,片桐孝洋,星野哲也,大島聡史,河合直聡,永井亨,3Dify:対話型分散フレームワーク -RAGを用いたマルチDCC対応プロシージャル3D生成LLMエージェント,情報処理学会 第87回全国大会,2025年3月15日.
成果物
- 林俊一郎,VibeCodeHPC - Multi Agentic Vibe Coding for HPC, https://github.com/Katagiri-Hoshino-Lab/VibeCodeHPC-jp, 2025年8月.
- 林俊一郎,3dify-project, https://github.com/3dify-project.
関連イベント
- JHPCN Field Workshop State-of-the-Art in Code Generative AI for High-Performance Computing(2025年12月5日,名古屋大学情報基盤センター)
- 第33回AT研究会オープンアカデミックセッション(ATOS33) 特別企画「LLMによる生成AIのHPC適用」(2025年7月28日,名古屋大学情報基盤センター)
- Second ITC-NU High Performance Computing Division International Seminar(2024年7月25日,名古屋大学情報基盤センター)
- Workshop on Numerical Computing and Software Productivity in Nagoya (WNCSP2023)(2023年8月30日,名古屋大学情報基盤センター)
研究参加者
随時更新します.
- 片桐 孝洋(名古屋大学 情報基盤センター 教授)
- 星野 哲也(名古屋大学 情報基盤センター 准教授)
- 椋木 大地(名古屋大学 情報基盤センター 助教)
- 森崎 修司(名古屋大学大学院 情報学研究科 情報システム学専攻 准教授)
- 大島 聡史(名古屋大学 情報基盤センター 招へい教員 / 九州大学 情報基盤研究開発センター 准教授)
- 林 俊一郎(名古屋大学大学院 情報学研究科 修士1年)
- 森田 光貴(名古屋大学大学院 情報学研究科 修士1年)
- 樹神 宇徳(名古屋大学 情報学部 学部4年)
- 三笠 諒(名古屋大学 情報学部 学部4年)
- 磯部 晃輝(名古屋大学 情報学部 学部4年)
- 阪口 修吾(名古屋大学 情報学部 学部4年)
- 内田 啓太(名古屋大学 情報学部 学部4年)
研究助成
- 次世代エッジAI半導体研究開発事業「テーマ(1) 高効率自動設計による次世代AI回路・システム」採択課題「ローカル LLM 支援によるエッジ AI 半導体の次世代高効率設計基盤の創出」(代表者:名古屋大学 石原亨 教授)の、主たる研究分担者(名古屋大学 片桐孝洋 教授)として参加している。
- HPCI整備計画調査研究事業における採択課題(3)運用システム(計算機)整備計画調査研究(代表機関名:国立研究開発法人理化学研究所,事業代表者:佐藤 賢斗)の分担機関(東海国立大学機構 名古屋大学、分担機関代表者:星野哲也 准教授)、および採択課題(4)量子等ハイブリッド(連携)運用環境調査研究(代表機関名:国立大学法人東北大学 事業代表者:小松 一彦)の分担機関(東海国立大学機構 名古屋大学、分担機関代表者:片桐孝洋 教授)として参加している。
- JHPCN2025採択課題(jh250015)ソフトウェア工学による自動チューニング技術の新展開 (課題代表者:片桐孝洋)https://jhpcn-kyoten.itc.u-tokyo.ac.jp/abstract/jh250015
更新履歴
- [2025年12月22日] 研究発表等および研究助成の情報を更新しました.
- [2025年11月27日] 研究発表等の情報を更新しました.
- [2025年11月26日] 研究発表等の情報を更新しました.
- [2025年10月2日] 研究発表等の情報を更新しました.
- [2025年8月19日] 研究発表等の情報を更新しました.
- [2025年8月8日] 研究発表等の情報を更新しました.
- [2025年7月8日] 研究発表等の情報を更新しました.
- [2025年7月4日] 研究発表等の情報を更新しました.
- [2025年6月30日] 研究発表等の情報を更新しました.
- [2025年4月16日] 本ページを開設しました.
お問い合わせ先
椋木 大地(名古屋大学 情報基盤センター) (mukunoki <at> cc.nagoya-u.ac.jp)